洗濯物干しを天井から吊り下げる時は、川口技研のホスクリーンを使います。取り付け場所を決めるため、天井裏に強い下地がある位置を下地探しを使って特定します。

解説
洗濯したものを乾かしたいのに、天気があまりよくなく、室内でいろいろな出っ張り部に干している方もいることでしょう。
天気とは関係なく、防犯のため洗濯物を外に干すのがためらわれたり、アレルギーで花粉やほこりを洗濯物につけたくない方は、室内物干しがないと大変です。
室内物干しは、天井に自分で後から取り付けることもできます。とはいえ、重たい洗濯物をつるしますので、その重量に耐える下地にネジで取り付ける必要があります。
力を支えられる下地を見つけ、天井を補強する方法を説明していきます。
室内物干しとは?
室内物干しの器具の中で有名で、個人でも手に入りやすいのは、川口技研の「ホスクリーン」(干す・クリーン)です。
ホスクリーンの標準品は、物干し竿を保持する金属ポールを天井から吊るす構造になっています。
したがって、ホスクリーンの土台は、天井の強い部分に固定してあげないといけなくて、それが下地です。
下地とは?
下地って何でしょう。
よく使う場面は、化粧の下地でしょうか。同じ概念で、住居の塗装や自動車の塗装でも下地塗りなどと言いますね。
つまり「表からは隠れて見えないけど、下に広く層が存在する」ことで大事な機能を持つことです。
一方で、アパート・マンションなど建築物における下地とは、表から見えない
・天井を支えているコンクリート製や金属製、木製の梁
・建物の枠組みとなっている柱や梁
のことです。
冒頭に述べた下地の概念は、広く一様に存在するけど副次的なものでしたが、建築物の場合の下地は、
・ところどころにしか存在しない
・下地が、建物の構造や強度をほとんど決めている
という違いがあります。
天井の下地位置は?
もし、ホスクリーンの土台を付けたい天井が、ワンルームで下のような感じだったとしましょう。

奥には外への出口があり、両側は壁です。左側の天井には梁と思われるでっぱりがあります。
よくある天井の構造を透視してみましょう。

太い梁に対し直角に渡した小梁(こばり※)があり、天井裏に電灯配線を引き回してある、といった施工になります(※正確には、野縁という名称です)。壁の裏には間柱があり壁板を打ち付けてありますが、図は省略します。
下地は太いほど、強度があります。そうなると、一番左の太い梁に固定するのが良いと考えますが、あまりに物干し竿が壁に近いと洗濯物が壁と当たってしまいます。
この部屋では赤い矢印で示す通り、太い梁と接合された小梁はありますので、小梁に対してホスクリーンの土台を固定しましょう。天井に張り巡らされた小梁のところ以外に取り付けると、洗濯物の重さに天井仕上げの石膏ボードが耐えられず、取り付け部が割れてしまう恐れがあります。
なお、梁の位置や間隔は一例であり、きちんとした方法で下地を探し当ててビスを打つことで、取り付けたときの失敗を未然に防ぐことができます。
下地の探し方は?
まず、道具がいらない簡単な方法からです。
天井の石膏ボードを、人差し指や中指の第二関節でトントンと叩いて、違う場所ごとの音を聞き比べましょう。
木材の下地があるところは叩いた時の音が響かず、やや低い音になります。
他方、下地がないところは、石膏ボードの裏側の屋根裏空間に音が響くので、高い音になります。
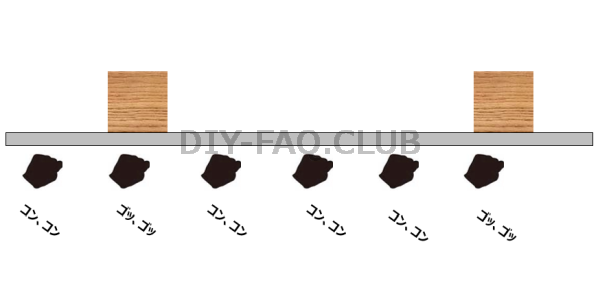
ボード裏の下地を探す工具
アパート、マンション住まいの場合、隣や階上の住民に気兼ねして、音を出して下地を探すのはできないこともあります。
そんな場合は、ホームセンターで入手できる、石膏ボードの下地探し針を使うとよいでしょう。

この工具は、先端に細い針が付いています。石膏ボードにこの針を刺し、そこに下地が無ければ貫通して最後まで抵抗なく突き抜けます。下地がある場所は針が下地の柱に突き当たるため、そこから先に進入しません。この違いで、下地の位置が判断できます。
針で壁に穴を開けて大丈夫?と思いますよね。とても細い針を使っている上、普通は石膏ボードには仕上げの壁紙が貼ってありますので、針を刺した後の穴は目立ちません。簡単な仕組みですが、効果は絶大ですのでオススメします。
とはいえ、天井のクロスが凹凸がなく真っ白で、クロスに針穴を空けると目立ってしまう。あまり自宅を傷つけたくないな、とお考えの方は、非接触で下地を調べる電子式の下地センサーを使いましょう。
壁・天井の表面でセンサーを上下左右に滑らせると、下地があるところではLEDが点灯するので、点灯する範囲をマーキングして下地を特定します。
このセンサーならば壁紙を傷つける恐れはありません。
更には天井に限らず、単にフックなどを壁に取り付けたいときでも、下地の場所が分かるとしっかりと固定できますので、ぜひ持っておきたい道具です。
天井まで手が届かないときは?
天井に手が届かないと、指も、針も、センサーも使えませんので、下地探しは難しくなります。それでも、やみくもにホスクリーンを取り付けるのはおすすめしません。
こんな時は、天井に届く長い硬い棒で、天井を叩いてみましょう。先に述べた、指の関節でトントン...と叩くのと同じく、音で判断します。
木でも、金属でも、プラスチックでも、固ければ良いです。ちなみに、伸縮ポールはゴムが両端についているので音がうまく出ません。あるいは、硬い棒がなければプラスチックハンガーの角などでも代用できます。
まとめ
天井に室内物干しをつける時は、天井裏がわからないと不安ですし、失敗も回避しにくいです。
支えの限界を超えて急に物干しが落ち始めたら、原状回復をするのは大変です。先回りして、安心して室内物干しを使いたいですね。




