木工用ボンドでくっつかないものには、プラスチック全般、金属、ゴム、ガラスや陶器などがあります。素材によらず何でも接着したいときは、多用途のボンドや二液タイプのボンドを使うとよいでしょう。
解説
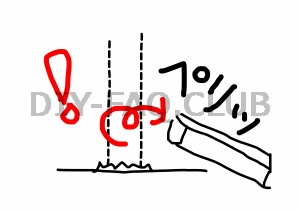
木工の作業で、木材同士を接着する場面では木工用ボンドのお世話になります。
学校の工作の授業を皮切りに、ちょっとした小物の製作、木工製品の剥がれの補修などに活躍します。
木工ボンドは100均でも手に入るので、何にでも使える万能な感じがしますが、現実にはつかないものがあります。
以下で説明していきます。
木工ボンドでつくものは?つかないものは?
つくものは、木材や紙、布などです。
つかないものは、プラスチック、金属、ゴム、陶器、ガラスなどです。
基本的な木工用ボンドは、木工用接着剤の代名詞となった木工用ボンドをはじめ、一般的には酢酸ビニル系の樹脂が主成分です。
元の出発原料が石油なこともあり、油には溶けやすいのですが水には溶けません。
これを水に溶けるように化学処理をして、液体状にしています。
木工用ボンドでくっつくというのは、接着成分を溶かした水が消えることです。
大気中に蒸発したり、接着する基材に吸収されたりして、ボンドの液体の中から水分が飛ぶとくっつきます。
木材や紙、布は、接着する基材がすき間を多く持っていて水分が吸収されるため、接着する樹脂も染み込むことでよく接着します。
反対に、金属とプラスチック、陶器は水を通しませんのでボンドの水分は大気中に蒸発するしかなく、そもそもくっつけたいもの同士でボンドを挟みこんでいますから、水分が逃げません。
プラスチックと木、金属と木のように、貼りたい片方が水分を吸収してくれればくっつきます。
しかし、ボンド成分がプラスチックや金属に触れても、表面的にしか引力がありませんので、あまり強くくっつかないです。
難接着基材と親和性があるプライマーと呼ばれる中間材を先に塗布し、そこにボンドを塗る方法もあります。
プライマーと木工用ボンドの相性もありますので、事前に説明書をよく確認しましょう。
多用途のボンドとは?

木工用と商品名で書きながら、塩ビや金属との接着にも使えると宣伝する多用途タイプの木工用ボンドもあります。
これは酢酸ビニル系樹脂にエチレンを反応させた樹脂(EVA)を主成分としていて、樹脂や金属にもくっつきます。
EVAの反応のさせかたの違いで、接着性や成型性、柔軟さなどを様々に変えられるので、家庭用ボンドとして製品化されているのに加えて工業用で広く使われています。
水性ですので、小さいこどもが使っても安全です。初めの一本なら、多用途ボンドの方が便利です。
万能なボンドとは?

あれは大丈夫、これはダメ、そんな面倒なことを言わずに、なんでもくっつくボンドはないの?
木工用ボンドにこだわらなければ、ほとんど何でもくっつく、失敗しない接着剤は他にもあります。
その一つが、ボンドクイック5です。木材はもちろん、プラスチック全般、金属、ガラスや陶器などは得意で、くっつかない接着物は少ししかありません。
二つの色の違う接着剤を別の場所に出して、絵具の色を混ぜるように混合してから接着したい場所に塗ると、5分で固まり始めます。
二つの接着剤を同じ量だけ混ぜて反応させますので、水が飛ぶとか塗りすぎも関係なく、失敗せず硬化します。
混ぜ合わせる接着剤は初めてかもしれませんが、難しいことはありません。確実さを求めるならこちらですね。
