木材を準備するとき、ラブリコは使い方説明で指定された数字よりカットを減らし、マイナス90mm以上、95mm以下の範囲で長さを決めるとしっかりと固定できます。ウォリストは推奨されたマイナス60mmから変えないでカットしましょう。すでに木材を短くカットした後なら、木の端材などでかさ上げします。
(ラブリコの木材長さのギモンが解消したら、DIYに進みましょう)
目次
解説
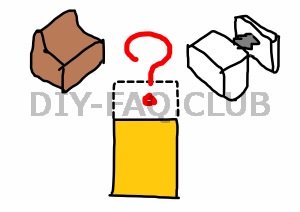
賃貸でも、狭いワンルームや1Kでも、一人暮らしの作業で2×4材の収納を作れる!
突っ張り式なので2×4材や1×4材(ワンバイフォー)の柱を立てても賃貸に傷をつけない!
という機能的なDIY部品「ラブリコ(labrico)」「ウォリスト(walist)」が人気です。
しかし、この手のグッズは、ツーバイフォー材をカットするときに長さを失敗しやすいところで、
マイナス何センチなら良いのか、95mmというけれど間違えて90mmになったらダメなのか、
使い方の説明に寸法の調整範囲が書いてない、など、疑問がわきます。
ここでは、突っ張り方がジャッキ式の点で共通のラブリコ、ラブリコアイアン、ウォリスト柱のカットサイズの許容幅やおすすめのカットサイズを説明します。
お知らせ:ディアウォールの長さの説明は別記事に移動しました。
┗━━ディアウォールの木材カットは何センチがベスト?
許容幅は?【結論】
はじめに、それぞれ部品ごとの結論を表にまとめました。
製品に記載された公称のカット寸法、公称通りでの状態、おすすめカット寸法の一覧です。
急ぐ方はこの表だけ見れば、この記事の結論がわかります。
| 公称カット寸法 | 公称通りだと | おすすめ | |
| ラブリコ アジャスター | 95mm | ちょうどよい もっと改善できる | 90~95mm |
| ラブリコ アイアン | 75mm | ちょうどよい もっと改善できる | 70~75mm |
| ウォリスト | 60mm | 最適 | 変えない |
以降の説明では、部品ごとの動作幅を測定した結果とおすすめのカット寸法の説明、そして、すでにカットしてしまった後に長さ合わせをするリカバリー方法を説明します。
カット長さの決め方は?
最適なカット長さを求めるにあたって、まずは公称のサイズを確認しておきましょう。
各製品の使い方の説明書には、使用する2×4材をマイナス何センチの高さで準備するか示されています。
・ラブリコアジャスター→マイナス95mm
・ラブリコアイアン→マイナス75mm
・ウォリスト→マイナス60mm
公称のサイズがどのような思想にもとづいて決まっているか触れてから、木材カットの誤差範囲や、もっと良い調整ができる許容範囲を説明します。
ラブリコアジャスターとは?


ラブリコアジャスターの構造のポイントは、
- 木材の天井側に取り付け上キャップには、ジャッキで天井を突っ張る天キャップのネジ胴を入れる縦穴(バカ穴)があいている、
- バネの動作範囲はほとんどない、バネの突っ張り力は小さい
という点です。
ラブリコアジャスターの設計寸法は?
実際の調整幅を、上キャップ、天キャップで確認します。
もっとも伸ばしたとき

天キャップのネジ胴が上キャップの縦穴にぎりぎり掛かる程度の位置で、天キャップの天井面は木材の先端から約118mmの位置になりました。
ただし、この位置ではネジ胴が上キャップから外れる恐れが高く、危険です。
もっとも縮めたとき

天キャップのネジ胴を上キャップの縦穴に最大に押し込む位置で、天キャップの天井面は木材の先端から約80mmの位置になりました。
よって、118-80=約38mmの動作範囲があります。
中間の位置のとき

天キャップのネジ胴の約3分の1が上キャップの縦穴に入る位置で、天キャップの天井面は木材の先端から約93mmの位置になりました。
多少ぐらつきは出るので、もう少しネジ胴を入れた方が安心です。

下キャップの寸法も確認します。
下キャップの床面は木材の先端から約7mmの位置になりました。
ラブリコアジャスターの調整幅は?
| 木材長に追加される長さ | 数値 | 状態 |
| 最大側 | +125 mm (天井側118mm/ 床側7mm) | ・ねじ胴を一番伸ばした状態 ・固定はゆるく、ネジが倒れる |
| 最小側 | +87 mm (天井側80mm/ 床側7mm) | ・ねじ胴を上キャップに一番押し込んだ状態 ・突っ張っていない |
ラブリコアジャスターを取り付けて、木材長から増える寸法は+87ミリから+125ミリです。
公称カットサイズのねらいは?
ラブリコの公称取り付け寸法は木材長に対しマイナス95mmですので、最小側の87mmに近いですね。木材カットで調整できる範囲 125mm~87mmのうち、木材はあまり長さを詰めず約95mmの位置で使うことを推奨しています。また、95mmは設計上はぎりぎりではないため、木材長に多少の誤差があってもぎ吸収できます。
ネジ式ジャッキで突っ張り荷重をかけるので位置による力の差はありませんが、上キャップはのネジ胴の傾きを支える程度しか働かないので、木材長を大きくしてネジ胴を上キャップに押し込むほど安全です。
推奨よりカットを減らし、90mm以上、95mm以下の範囲でカットすると安心でしょう。
突っ張るほど安全だから、とやみくもにネジを突っ張ると、上部の板を突き破ってしまうトラブルを起こします。ご注意ください。
もうカットした、今から間に合う?
もっとカットを減らせば良かった、と思っても木材をカット済みだと困ります。せっかくですから、新しく木材を買わずにすませたいところです。三つの方法を紹介します。
木材でかさ上げ
まず、手持ちの木の端材で下キャップの中をかさ上げできないか検討します。下キャップに5mmの薄い木板を入れられれば、カット長を小さくしたのと同じです。
うっかりはじめから95mm以上をカットしてしまったときも、同じように下キャップの中でかさ上げすることを検討してください。
ディアウォールの下パッドを使う
次にやりやすい方法は、ディアウォールを手に入れて下パッドだけを流用することです。ディアウォールの下パッドは、肉厚が約13mmですので、ラブリコの下キャップとは6mmの差があります。
ディアウォールの下パッドに替えれば、カット長を6mm小さくしたのと同じことになります。
ラブリコの下キャップとディアウォールの下パッドは、同じ働きの部品です。混ぜて使っても問題ありません。
つなぎなおして全長を短くする
2×4の柱を何本も使うので、この際それぞれのカット長も全部そろえたいときは、いったん今の2×4材を適当な位置でカットして、ジョイント部品でつなぎなおす方法が良いでしょう。
ラブリコには、2×4材を連結するためのジョイント部品があります。二つのキャップを、別々の2×4材の端部にそれぞれ固定してから、後で組み合わせるしくみです。
このジョイント部品同士を組み合わせると木材長が26mm長くなります。
今の2×4材を、ジョイントしたい一本目と二本目の木材に切り直す時は、それぞれA mm、B mmとすると、A+B+26=新しく欲しい長さ、になるようにします。
このジョイントは、ラブリコのキャップのように2×4材にかぶせるだけではなくネジでしっかりと固定するので、外れる心配も不要です。
ラブリコアイアン、ウォリストとは?
ラブリコアイアン、ウォリストの両者を対比しながら説明します。
ラブリコアイアン

ラブリコアイアンの構造のポイントは、
木材の天井側に取り付けるアジャスターには、天井を突っ張る板には正ネジ(右ネジ)、2×4材を突っ張るコの字枠には逆ネジ(左ネジ)がついており、中間の雌ネジ胴を回すと互いに離れて突っ張る仕組み
という点です。
ウォリスト突っ張りジャッキ


ウォリスト突っ張りジャッキの構造のポイントは、
木材の天井側に取り付ける本体は、パンタグラフジャッキに似た、水平方向の力図天井を突っ張る垂直の動きに変換する構造
となっています。
調整ネジは水平バネの片端固定位置を変えるためのもの、固定位置を最大するとジャッキが最も上方へ上がるしくみです。

ラブリコアイアン、ウォリストの両方とも、床側のキャップは元からなく、2×4材や1×4材の床側に取り付けるキズ防止シートが添付されています。約2mm厚で同等です。
設計寸法は?

両部品のジャッキを最も伸ばした状態の位置で、ラブリコアイアンは木材の先端から約102mmの位置、ウォリストは木材の先端から約76mmの位置になりました。
ラブリコアイアンは、中間の雌ネジ胴から突っ張りの雄ネジがほぼ出てしまい、この状態で使うのは危険です。

両部品のジャッキを最も縮めた状態の位置で、ラブリコアイアンは木材の先端から約62mmの位置、ウォリストは木材の先端から約40mmの位置になりました。
ラブリコアイアンは約50mmの動作範囲があります。ウォリストは約36mmの動作範囲です。

ただし、ウォリストはネジのジャッキ力が掛かり始める位置まで上げてあげる必要があり、約54mmあたりから上でネジのジャッキ力が掛かります。
ラブリコアイアンの調整幅は?
| 木材長に追加される長さ | 数値 | 状態 |
| 最大側 | +104 mm (天井側102mm/ 床側2mm) | ・ジャッキを一番伸ばした状態 ・ジャッキがぐらついて突っ張れない |
| 最小側 | +64 mm (天井側62mm/ 床側2mm) | ・ジャッキを一番縮めた状態 ・突っ張れない |
ラブリコアイアンを取り付けて、木材長から増える寸法は+104ミリから+64ミリです。
ラブリコアイアンの公称取り付け寸法は木材長に対しマイナス75mmですので、下部シートの肉厚(約+2mm)を除くと、ジャッキの動作範囲 約102mm~約62mm(安全側)のうち約73mmの位置(=75-2)で使うことを推奨しています。
推奨位置は、雄ネジ雌ネジの掛かり数が多めの、荷重を多く受けられる安全側です。
推奨よりややカット長を減らし、70mm~75mmなら更にネジの掛かり数が増え、強度が増します。
もしカット長をより減らす方向へ変えたいときは、部品にキャップ類がないためスペーサを入れる方法は難しいです。
中間のジョイント部品を使って、新しく全長をする設定するほうがよいでしょう。
(詳しくは上の方の、ラブリコアジャスターの項をごらんください)
ウォリストの調整幅は?
| 木材長に追加される長さ | 数値 | 状態 |
| 最大側 | +78 mm (天井側76mm/ 床側2mm) | ・ばねが効いていない状態、突っ張っていない |
| 最小側 | +42 mm (天井側40mm/ 床側2mm) | ・ばねを完全に押し込んだ状態 ・キツキツすぎ、この状態で取り付けは難しい |
ウォリストを取り付けて、木材長から増える寸法は+78ミリから+42ミリです。
実際にはバネのジャッキ力がかかり始めるのはもう少し上で、最小側は、木材長に対し、プラス約56mmです(天井側54mm/ 床側2mm)。
ウォリストの公称取り付け寸法は木材長に対しマイナス60mmですので、下部シートの肉厚(約+2mm)を差し引いて、ジャッキの動作範囲 約76mm(バネ弱)~約56mm(バネ強)のうち約58mmの位置(=60-2)で使うことを推奨しています。
もともとバネの力が強い方が推奨位置ですので、さらにカット寸法を減らすことはないでしょう。
反対に、カットが多く木材が短めになっても、バネ力には余裕がある作りです。
まとめ
ラブリコは、調整幅の中で少しネジの押し込みが深くなる方向にいじると、安定して固定できるようになります。
一度収納を作り上げてしまうと、後から修正するのは難しいですので、作っているときに微調整をいれておくのが一番です。
ラブリコアイアンやウォリストは、安定して固定ができる調整の幅が広いので、木材カットの調整に自信がない方は初めからそちらを使うのも良い方法です。



